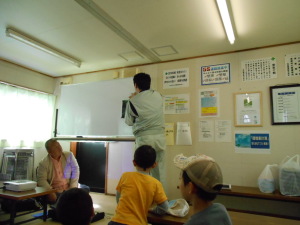さる9月20日(土)に、大同舗道(本社・札幌市中央区)と当NPOの共催による「札幌市豊平区、南区のインフラの歴史を学ぶ見学会」と称した日帰りバスツアーを実施しましたのでご報告致します。
ホームページ等で募った一般の方も交えての総勢19名にて、知る人ぞ知る(知らない人は何にも知らない)ディープな札幌の歴史を、当NPOの理事でもある佐々木実氏の解説を聞きながら探索をする、といった一風変わったバスツアーです。
AM9時に大同舗道の平岸にある工事事務所をスタートしました。
まず最初に訪れたのは、「本願寺街道終点碑」です。伊達を起点にこの地点までを当時のお坊さん達が手作業で道路を作ったわけです。こんな街の中に有るとは地元に住んでいる人も知らなかったという隠れスポットです。
次に立ち寄ったのは石切山街道の碑。
石切山街道の碑から徒歩で向かったのは、旧定山渓鉄道の駅だった建物です。現在は、石切振興会館として地元の方達が大事に利用しています。この日はあいにく休館日で中には入れませんでした。
その向にある石山ポスト館は、札幌軟石で建築された札幌でも数少ない洋風建築の郵便局でした。さっぽろ・ふるさと文化百選にも選定されているようです。
なんと今でも現存する本願寺道路を散策です。非常に細い道ですが、当時は馬車なども通ったとのこと。
また、この付近には今でも当時の「通行屋(宿泊施設や休憩所)」として着任した方のご子孫がそのままお住まいになっているのに一同はびっくり。
簾舞中学校入口付近にある本願寺街道跡(碑)で本日2枚目の記念撮影です。
次いで旧道の難所だった七曲りと板割坂を通過し、旧滝ノ沢駅に今ものこる二見桜を見学しました。
ここで本日3枚目の集合写真をパチリ。
再びバスにゆられて、定山渓の温泉街に到着です。でも目的は温泉ではなく、こちらの北海道三景の碑。
実はこの付近が定山渓鉄道の終着駅でした。ちなみに、北海道三景とは、定山渓、洞爺湖、そして利尻富士の3か所だそうで、いずれも小樽新聞社により碑が建てられたそうです。
車中で佐々木氏による解説を聞きながら、あっという間に中山峠にある大同舗道の工事事務所へ到着しました。
ここで担当している工事の概要説明を受けました。参加した子供たちも真剣に聞いています。
そしてお楽しみの昼食です。大人には幕の内弁当、そして子供たちには写真のドラえもん弁当です。とてもおいしかった。
中にはシャケのおにぎりやハンバーグなど、子供たちが好きなおかずがぎっしり。
中山峠に向かう途中で、大同舗道が担当している工事現場へ立ち寄りました。工事は夜間に行われているので、日中は作業機械が静かに休んでいます。子供たちは乗ったり下りたりと興奮気味です。やはり子供は建設機械が好きなんですね。
目の前には、舗装が終わった真新しいきれいな道路が続いています。静かで快適に走れそうですね。
あと少しで中山峠の頂上ですが、こんなところにも定山渓国道の碑が建っていました。
なので4枚目の集合写真です。
ここは望岳台と言って景色が大変に良い場所です。
ここから見える山が右に向かって高くなっていくのが右肩上がりのグラフに見えるのだとか・・。
たしかに右肩上がりのグラフにように見える!世の営業マンは一度は拝んだほうが良さそうです。
いよいよ中山峠の頂上に到着です。ここで我々が目にしたのは、不思議な形の3本の塔。
よく見るとこれはアスパラガスの形なのです。
すぐ脇には、「アスパラガス発祥の地」碑が建っていました。
岩内町出身の下田喜久三さんが日本で初めて栽培に成功し、中山峠のある喜茂別町で本格的に栽培がはじまったとあります。
それでここに塔が建っているんですね。
そして、この中山峠の頂上に建つのは、現在の国道230号線のベースとなった本願寺道路を作った現如上人の像です。
この人がいなければ230号線のルートも今とは違っていたのかもしれませんね。
それとこの方、なんと道路を作り出した時の年齢は19歳だったそうです。
当時東本願寺は徳川幕府よりだったため、明治維新後の新政府からその存続を得るために、伊達と札幌を結ぶ道路工事を出願したとされています。
中山峠では、各自自由時間を過ごしました。あげいもを食べたり、ソフトクリームを食べたりと、地元北海道の味覚を存分に楽しみました。
帰途はやや時間が足りなくなってしまい、大同舗道の羊が丘線バリアフリー工事を見学し、有名なアンパン道路を通って出発地点まで駆け足で戻りましたが、笑いあり、驚きありでとても楽しいプチツアーとなりました。参加された方はみな満足したようです。
このような企画にご賛同を頂いた大同舗道の皆様、大変ありがとうございました。またコース設定や解説などを担当された佐々木さん、大変お疲れ様でした。また次回の企画を楽しみにしたいと思います。
尚、当NPOでは、これからも建設業の皆様の果たしている社会的な役割やその貢献内容を広く知らしめるための活動を行って参ります。ご興味のある方はぜひお知らせください。